MASDAC NEWSとは、株式会社マスダックさまが発行されている広報誌です。
株式会社マスダックさまは高品質な製菓機械を提供されている企業です。
https://www.masdac.co.jp/
弊社では「丹波やながわ」東京春日店に全自動どら焼機を導入しています。
以下掲載文
User Interview 企業探訪
”丹波三宝”の菓子で風土に新たな交流を生む
株式会社やながわ・柳川拓三社長
小豆の王様“丹波大納言”産地、兵庫県丹波市春日町でやながわは、1892(明治25)年の創業以来4代にわたり地場の産物を広めて地域を盛り立てている。30年前には地元が誇る“丹波三宝”(小豆、黒大豆、栗)の加工業を興し、この20年は製菓を主軸に小売業も展開。7年前には地元出身で徳川3代将軍家光の乳母だった春日局の縁を辿り東京にも出店。昨夏からは春日通りの角地に移り、丹波大納言のあんを挟んだ焼きたてどら焼「どら福」を主力に新たな客を惹きつけている。
丹波の「夢の里やながわ」本店は、神戸から車で約1時間。山並みと農地が広がるのどかな風景の中にある。看板には「丹波風土」と掲げている。秋冬の朝夕は霧に包まれ昼夜の寒暖差が激しいその風土により、いずれも大粒で艶があり甘味が濃厚な丹波三宝が育まれてきた。
「本店のコンセプトは、丹波素材で奏でるライブステージ。産地ならではの味や季節感を楽しんでほしいと思い、12年前、田んぼだった加工場の隣に建て替えました。奥まった場所で客が来ないのではと心配されましたが、立地で選ばれる店ではなく、目的をもって来てもらう店を目指してきました」
今では店舗入口から500m余り、車の列ができることもあり、多い日には800個以上売れる季節限定の「和のモンブラン」を目当てに、昨秋の平日も開店前から客が並び、季節のスイーツが楽しめるカフェも昼には8卓すべて客で埋まっていた。
売り場には前述の商品のほかに丹波の地場産品を活かしたシュークリームやプリン、バウムクーヘンやサブレ、最中やぜんざいなどの菓子類と、煮豆や栗の甘露煮などの惣菜類、さらに緑茶も並んでいる。
「弊社は物産の商いで育った会社です。私が幼い頃は松茸が山のように採れ、両親が大阪のなんば高島屋などへ卸し、また、背丈程ある桶で筍を灰汁抜きして業務用の缶詰などをつくっていました」
1970年代には製茶が主業となり、自身は大学卒業後、静岡での製茶見習いを経て家業に就いた。
「お茶は私のものづくりの原点です。荒茶を仕入れ精選して火入れをする製茶では、素材の力を引き出すことが大事。その技術は島国独自の風土で育まれた日本の料理に通じる文化であり、その考えが今の特産品加工の基本になっています」
また、茶商(製茶問屋)時代、百貨店の物産展で重ねてきた対面販売の経験が、その後の事業転換の動機や経営方針に繋がっているという。
「宛名は手書きで封書DMを1000通近く出し、販売では、お茶に込められた想いを伝えることで、多くのお客様が会話を楽しみに会いに来てくださっていました。また、おいしかったという声を生産者に届け、その双方の間で私も励まされ、大きなエネルギーをいただいていました」
しかし、茶の飲料が出回り製茶業は縮小。荒茶の生産者を守れなかった悔しさをバネに、生産者と消費者を繋ぐ中間業者の役割をより意識して、“材供給の地”だった丹波を特産品の加工や小売の2次、3次産業で活性化させる挑戦を始めた。
まず、1988年、翌年放送のNHK大河ドラマ「春日局」に合わせて黒豆の乾燥甘納豆を仕入れ、「お福豆」(福は春日局の名)として地域の博覧会で販売。その商品化を機に自社で黒大豆の加工を始め、1995年には元筍缶詰工場を改修して丹波三宝の加工を本格化。2001年には道の駅「丹波おばあちゃんの里」の開設、検討委員会にも関わり、2005年には工場脇に「夢の里やながわ」の本店を、京都府福知山市に支店を開いた。
「最初は小さな店でしたが、店名の夢に志と希望と挑戦、里にその広がりへの想いを込めました」
菓子製造では職人を招き、和テイストの洋菓子に続いて和菓子も増やし、2009年には大阪の阪神梅田本店に丹波栗を中心とした菓子専門店も出店した。
「栗は収穫期が短く、鬼皮剥きなどに手間がかかり、灰汁の排水処理に費用も嵩む。しかも丹波栗の収量は昭和50年代をピークに7割減。だからどこも手掛けず珍しいからと依頼があり、自分たちを磨くいい機会になると考え出店しました」
出店時に開発した、収穫直後につくる丹波栗ペーストをたっぷり使った「和のモンブラン」は、本店を拡張した2013年に農水省「第一回地場もん国民大賞」で審査員賞を受賞。店の名物となった。
そして2018年には、百貨店の改装を機に大阪の店舗は閉じ、東京に支店を開いた。
「大阪の9年間で評判は高まり、得るものは多かったのですが、もっと“想い”を伝えたい、丹波三宝を広めたいとの思いが募り、東京に春日通りがあると知り訪ねて出店を決めました」
初めて通りを訪ねた際、ゆかりの春日局が眠る文京区麟祥院(りんしょういん)を参拝したところ、偶然前年、100年ぶりに命日の法要を行い、住職が丹波の春日局生誕地を訪れ、道の駅でやながわ製造の「お福豆」を買っていたという。以来、毎年法要には菓子を提供している。
「縁尋機妙(えんじんきみょう)・多逢聖因(たほうしょういん)という言葉がありますが、まさに縁が縁を呼び、よい方に進んでいきました」
昨夏はさらに人通りの多い本郷の交差点の「かねやすビル」に移転した。江戸期に歯科医が歯磨き粉を商った旧跡で、1階の店は長年閉じており何度か手紙を送っても返信はなかったが、他の物件を契約する寸前、初めて連絡があり成約。その後、家主兼康家の先祖が奇遇にも丹波地方出身と知ったという。
新たな「丹波やながわ」東京春日店の主力「どら福」は生地にも丹波産の卵と兵庫県産の小麦粉を100%使用。全自動どら焼機を導入して毎日、焼きたてを販売している。
「都市の生活圏では日常的な商品を柱にしたい、経営視点では店を利益体質にしたいと考え、機械でおいしく量産できるどら焼を主力にしました」
売上の6割を目標に贈答用にも力を入れ、年末には生産量が小豆全体の1%に満たない丹波大納言の中でもさらに希少な原種をあんにした「極みの逸品 黒さや大納言小豆のどら福」も発売した。
「東京の店は、丹波へ誘う玄関口。近くに東大もあり全国から次代を担う人材が集っているので、各地と丹波との繋がりを生む店にしたい。また、引き続き本店を拠点に京阪神の交流人口を増やし、丹波を活性化したいと思っています。当初は丹波素材の高価な菓子など地元では売れないといわれましたが、外の人は地域ならではのものを求めて来ることがわかり、地元の意識も変わりました」
経営理念は「丹波伝心」。社員は約40名。
「丹波の特産を通してつくり手の心を伝え、心を込めて技を磨き丹波の味を伝える。その理念のもと、時流の中でいかに役割を見出すか。従業員には現状に満足せず、突き詰めてほしいと思い、様々な角度から目指す心を伝えています」
地域では兵庫県指定観光名産品協会の会長なども務め、広い視野で今後を展望している。
「グローバル化が進む今こそ、軸足は地元。産地は多くの共通課題を抱えていますが、企業や大学とも連携して地域ぐるみで思い切った策を講じ、丹波モデルとなる独自の課題解決を図りながら、賑わいづくりを広めたい。そして丹波の魅力を世界に発信し、丹波の風土とブランドを後世に繋いでいきたい。世代を超えて同じ志を持つ仲間を増やし、その夢を実現したいと思っています」




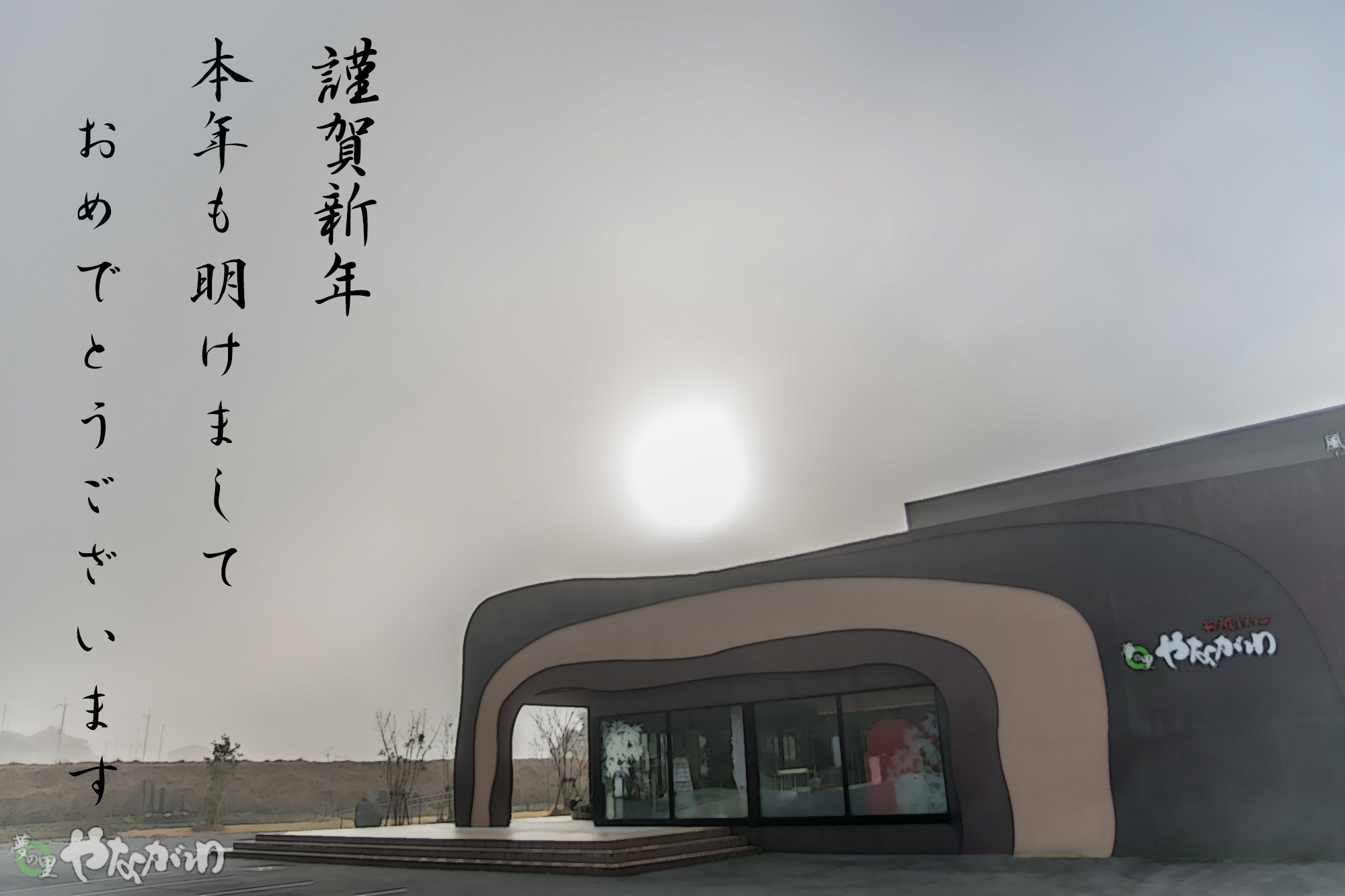


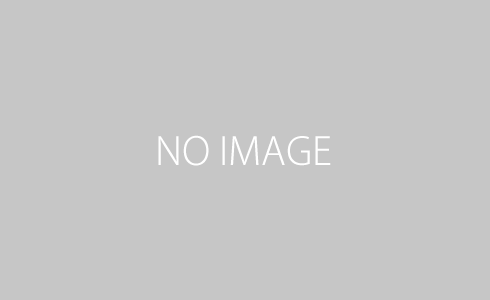



この記事へのコメントはありません。